こんにちは!胃弱OLのジャスミンです。
本日は皆さんが毎日触れる話題である「食事」とジャスミンも抱えている「胃炎」の関係についてお話ししていきます。
ところで皆さんは自炊していますか?外食が多めですか?
忙しい毎日の中で、コンビニやスーパーの加工食品はとても便利ですよね。
しかし、胃炎もちの私にとって「便利さ」と「胃の不調」は表裏一体なんです。
食後に胃もたれや胃痛を感じるとき、ふと「添加物が影響しているのでは?」と思うことがあります。この記事では、添加物と胃炎の関係について、科学的な視点と私自身の経験を交えてまとめます。
そもそも添加物とは?

食品添加物とは、食品の保存性や味・見た目を良くするために使われる物質です。代表的なものには以下があります。
- 保存料(ソルビン酸、安息香酸など)
- 発色剤(亜硝酸ナトリウムなど、ハムやソーセージに使用)
- 合成甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど)
- 化学調味料(グルタミン酸ナトリウムなど)
- 着色料・香料(見た目や香りを良くするため)
これらは国が安全性を確認したうえで使用が認められていますが、「胃が弱い人にとって負担になるか?」はまた別の問題です。
添加物と胃炎の関係
胃が弱い人にとって、添加物が含まれる植物をとるとどのような影響があるか、以下私が無添加生活をしてきたからこそ気づいた視点をまとめてみました。
消化負担が増える可能性
自然の食品と違って、人工的に合成された成分は分解に時間がかかるといわれています。私自身、合成甘味料や加工油脂が多い食品を食べたときは、胃の重さを感じやすいです。
胃酸分泌の刺激
強い旨味や香りを持つ添加物は、舌や嗅覚を刺激して胃酸が増える感覚があります。
私は胃酸が多く出すぎると胸やけやシクシク感につながることがあるので、こうした食品は控えめにしています。
炎症や過敏反応
人によっては添加物に敏感で、軽い不快感や炎症につながることがあるそうです。
私も「アレルギーというほどではないけれど、なんとなく胃が落ち着かない」と感じることがあります。汗
胃炎持ちが実践してきた、今日からできる工夫
以下、慢性胃炎持ちの私が実施してきた5つの工夫をお伝えします!今日からすぐ意識できることばかりなので、「ちょっと胃の調子が悪いかも…?」という人は試してみてください^^
原材料表示をチェックする習慣
カタカナだらけの食品は避け、できるだけシンプルな材料のものを選びます。
食品添加物は商品後ろの成分表示の「/(スラッシュ)」より右側の部分です。
自炊を増やす
塩・醤油・味噌など伝統的な調味料は胃にやさしいです。しかも味付けを調整できるのは、自炊の強みですよね。
外食・お菓子は量と頻度を調整
完全に避ける必要はなく、「週に1〜2回」など自分でルールを決めます。お菓子は手作りのケーキや当日中しか消費期限がもたないもの意外は、基本的に添加物が多く入っていることが多いです。
それでも、やっぱりお菓子って美味しくて手が止まらないんですよね…笑
飲み物も意識する
着色料や甘味料入りの清涼飲料水は控え、麦茶や白湯に切り替えると負担が減ります。私はコンビニで清涼飲料水を購入することをやめました。その分節約にもなったので一石二鳥でした^^
胃が荒れているときは添加物を最小限に
コンビニ食でも、おにぎり+サラダ+味噌汁など加工度の低い選択を心がけます。できるだけコンビニやファミレスではなく、定食屋さんで食べる、など手作りの食べ物を意識しています。
まとめ
添加物は私たちの食生活に便利さを与えてくれますが、胃炎もちにとっては不調の引き金になりやすいこともあります。完全に避けるのは難しいですが、「量・頻度・組み合わせ」を意識するだけで胃の調子が変わることを私は実感しています。
あなたは、加工食品を食べたあとに胃の調子が悪くなると感じたことはありますか?
インスタグラムでは、毎日をごきげんに過ごすための体調管理や健康の工夫をゆるっと発信しています!
よかったらのぞいてみてください → @jasmine.healthlog
「これ良かったよ」「こんなの実践してるよ」など、みなさんのアイデアも気軽にシェアしてもらえたら嬉しいです^^
■参照文献・参考リンク
- 厚生労働省|食品添加物の安全性について
- 消費者庁|食品添加物Q&A
- 日本消化器病学会|胃炎の基礎知識.
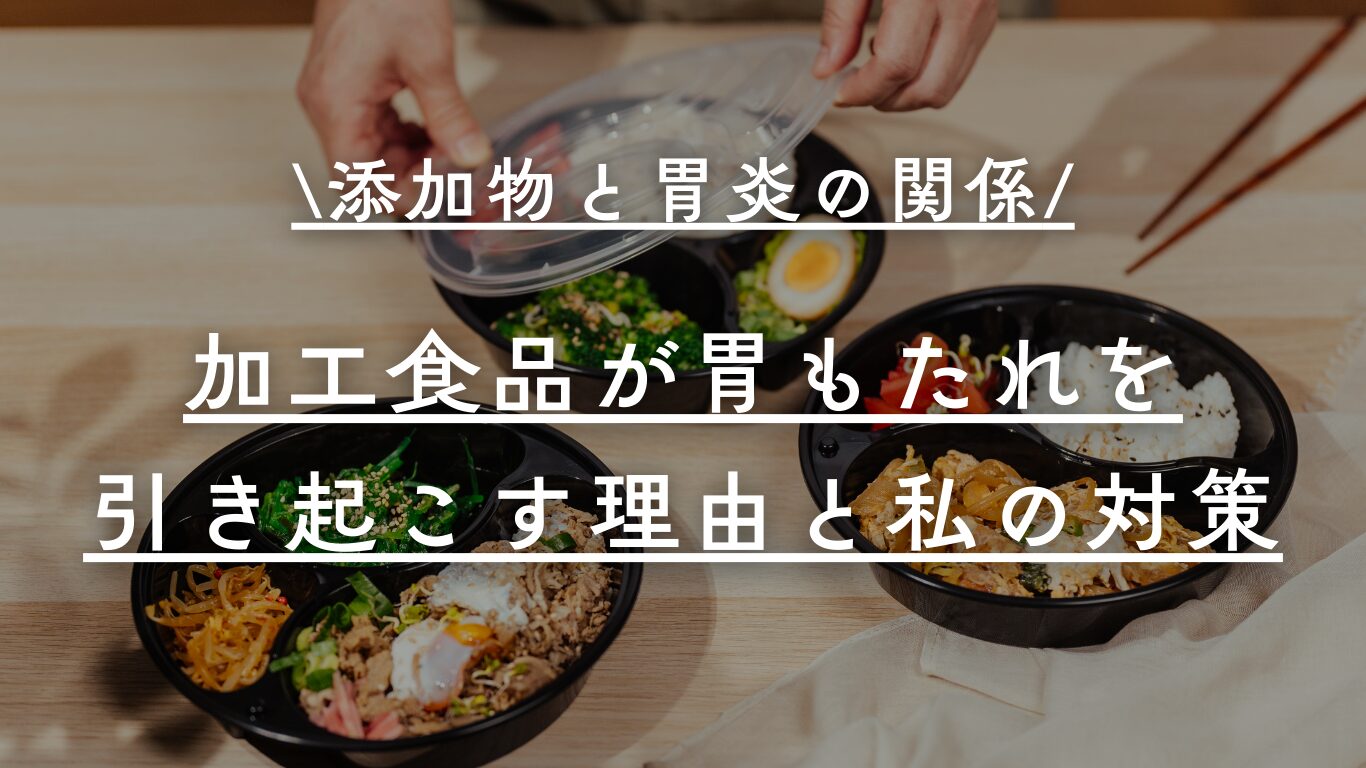


コメント