こんにちは、セルフケア研究家のジャスミンです!
10年以上、胃や体の不調に悩んできましたが、生活習慣を整えることで年間300日以上を快適に過ごせるようになりました。
スーパーやコンビニで食品を選ぶとき、原材料表示に「トレハロース」という文字を見かけたことはありませんか?
私も以前は「人工的な添加物っぽいけど、体に悪くないのかな?」と少し不安を感じていました。
でも調べてみると、トレハロースは実は私たちの身近な食品に広く使われている成分で、正しい知識を持つことで、過剰に不安を抱く必要はないことが分かりました。

トレハロースって何に使われているの?
健康に悪いって聞いたことがあるけど…

健康に悪いと一括りにできるものではなく、どう使われているか・どう向き合うかが大切。
この記事では、科学的な知見も交えながらトレハロースの基本をわかりやすくお伝えします。
トレハロースの正体や役割を理解して、自身で食材を選択する際の一助となれば幸いです。
- トレハロースとは何か
- どんな食品に使われているか
- 安全性についての基本的な情報
- 上手に付き合うためのヒント
食品の成分表示を気にしている方、添加物の基本を知りたい方、不安を少しでも減らしたい方におすすめです^^
食品添加物に関しては、ほかの記事でも詳しくまとめています。興味があればこちらの記事もぜひ参照してみてください。
トレハロースとは?

「トレハロース」という言葉を、食品の原材料表示で見かけたことはありませんか?
実はこれは、2つのブドウ糖が結合してできた糖質の一種で、きのこ・海藻・酵母など、自然界にもごく普通に存在している成分です。もともと植物や微生物の中でエネルギー貯蔵物質として使われているものであり、私たち人間も昔から食事を通して自然に摂取してきました。
特徴的なのは、甘さが砂糖の約半分程度と控えめである点です。味にくどさがなく、ほんのりとした自然な甘さを出せるため、料理やお菓子の味を引き立てる役割を果たします。
また、甘味度が低い分、カロリーも砂糖より控えめ。
そのため「低甘味・低カロリーの糖質」としても注目されており、冷凍食品・調味料・スイーツ・惣菜など、身近な加工食品で広く活用されています。
トレハロースが食品に使われる理由
では、なぜ多くの食品メーカーがトレハロースを取り入れているのでしょうか?
その最大の理由は、食品の品質を保ちやすくする特性があるからです。
例えば、トレハロースには次のような働きが知られています。
- 加熱・冷凍への耐性が高い:熱や低温に強く、調理・保存の過程でも成分が変化しにくい。
- 食感・風味を保つ作用がある:冷凍・解凍してもパサつきや硬さが出にくく、食品の食感が損なわれにくい。
- 変色・乾燥を防ぎやすい:酸化や乾燥による劣化を抑え、見た目をきれいなまま保ちやすい。
- 味をまろやかに整える:苦味・えぐ味・酸味などの角をとり、全体の味をまろやかに仕上げてくれる。
このような性質から、冷凍食品・惣菜・パン・和洋菓子・調味料など、ジャンルを問わず幅広い製品で重宝されています。食品業界では「味・見た目・食感をトータルで整えるサポート役」として欠かせない存在なのです(°_°)
トレハロースは体に悪いの?
「食品添加物」と聞くと、「なんとなく体に悪そう」と感じる人も少なくありませんが、現時点での科学的知見では、一般的な食品に含まれる量で健康被害が報告された事例はほとんどありません。
体内に入ったトレハロースは、消化酵素によってブドウ糖に分解され、体のエネルギー源として利用されると考えられています。
また、日本をはじめとする多くの国や地域で安全性の審査が行われており、世界保健機関(WHO)とFAO(国連食糧農業機関)の合同専門機関「JECFA」や欧州食品安全機関(EFSA)でも、食品への使用が正式に認められています。
つまり、「トレハロース=危険」というイメージは誤解であり、通常の食生活で摂取する範囲では大きな心配は不要とされています。
健康的に付き合うためのポイント
トレハロースは「避けるべきもの」ではなく、正しく知ってうまく付き合うべき成分です。大切なのは、「入っているかどうか」だけに注目するのではなく、食生活全体のバランスを見直すことです。
たとえば次のような工夫を取り入れると、より安心して食品選びができます。
食品表示を確認する習慣をつける
どんな添加物や糖質が含まれているのかを意識するだけでも、摂取量を自然と調整できます。加工食品ばかりに頼ら図、野菜・たんぱく質・未精製穀物などを組み合わせて食べると、血糖の急上昇や腸内環境の乱れを防ぎやすくなります。
大量摂取は避ける
トレハロースを一度に多量に摂取すると、腸内に水分が集まりやすくなり、一時的にお腹がゆるくなることがあります。特に腸が敏感な人や胃腸が弱っているときは、量に注意しましょう。
糖質のとりすぎに注意
トレハロース自体に問題がなくても、それを含む加工食品をたくさん食べてしまうと、総糖質量が増えて血糖コントロールに影響する可能性があります。
「トレハロース=体にやさしい糖だから」と安心しきらず、摂取量全体を意識することが大切です。
まとめ
トレハロースは、自然界にも存在する糖質であり、食品の品質を保ちやすくする目的で幅広く活用されています。
現在の科学的な知見では、通常の食品レベルでの摂取による健康被害はほとんど報告されていません。
重要なのは、「危険だから避ける」ではなく、「どう付き合うか」を知ること。
摂取量・食生活全体のバランス・自分の体の状態を意識しながら取り入れることで、より安心で健やかな食生活を送ることができます。
インスタグラム(@jasmine.healthlog)やX(@jasmine55health)では、胃弱でもごきげんに過ごす健康習慣やキャリア女子の体調管理の工夫を発信しています!
「忙しくても、キャリアも遊びも思いきり楽しみたい」
そのために、まずは自分の体調を整えることから。
同じ想いを持つ方とつながれたらうれしいです!
フォローして、一緒に心地よい毎日をつくっていきましょう^^
■参考文献
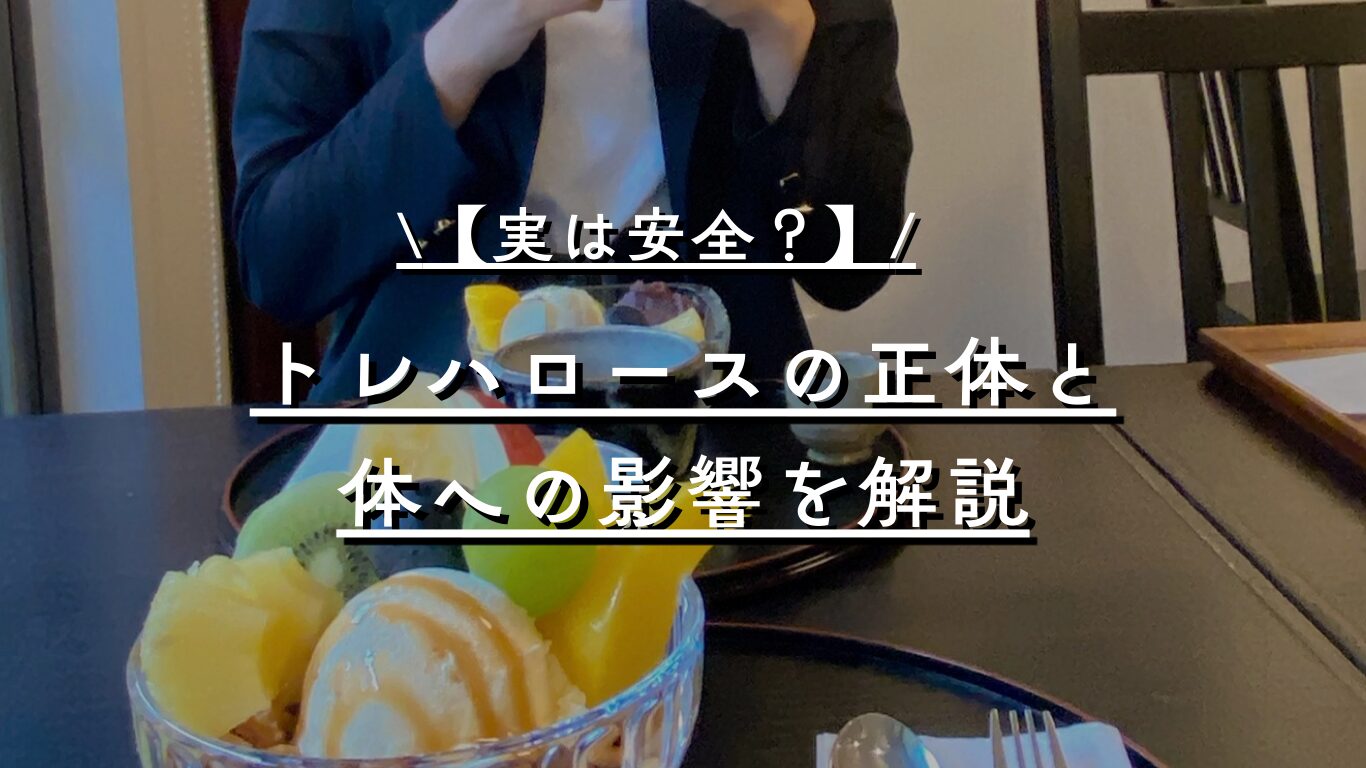




コメント